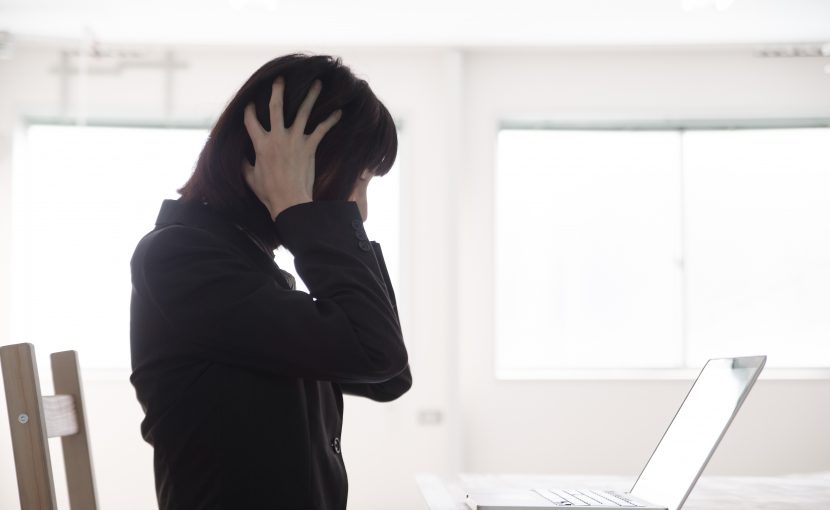梅雨時期や雨の日が続くと起こる頭痛やだるさなどの症状。これらの症状は気象病とも呼ばれ、天気や気圧が原因で起こっているかもしれません。
雨や低気圧が体に与える影響は以外にも大きく、体のバランスを崩してしまうことも珍しくありません。体からのSOSを自分では気づかないこともあります。梅雨時期に頭痛が続き、症状が続く場合には医療機関を受診しましょう。
ここでは梅雨時期の頭痛の原因や起こりやすい症状、対処法、予防法を専門医が解説します。
目次
天気の変化で体がツラい…気象病の原因は?
気象病とは、天気や気圧、寒暖差、湿度など、気象の変化によって起こる体調の変化やそれに伴う不調を言います。
ではなぜ、天気や気圧の変化で気象病が起こるのでしょうか?
頭痛やだるさなどの気象病は自律神経の乱れが原因です。
自律神経は、血液循環や呼吸、消化、体温調整などさまざまな機能を正常に保つためにコントロールしています。例えば、夏の暑い日に汗をかいたり、寒い日に体が震えたりするのも自律神経の働きです。しかし、梅雨時期のように天気が崩れたり気温が極端に変化したりすると、この自律神経が敏感に反応してしまいます。そうして体にさまざまな症状として起こるのが気象病です。
雨の日に起こる頭痛の原因は?
気象病のなかでも、頭痛を訴える人は多くいます。雨が降る日と頭痛はどのような関係があるのでしょうか?
こうした天気の変化によっておこる頭痛は、気圧の変化を感じ取る耳の中の内耳と呼ばれる器官で起こります。内耳で気圧の変化を感じ取ると、自律神経のうちの交感神経が活発に。この交感神経が活発になると、体温を上昇させたり、血管を収縮させたりします。
この血管を収縮する働きによって、頭痛を引き起こすと考えられています。
女性は特に気象病になりやすい!
気象病は年齢や性別に関係なく、気圧の変化で誰にでも起こります。しかしその中でも月経のある女性に起こりやすいことが分かっています。
女性は月経があることで、周期的に女性ホルモンのバランスが変化しています。このホルモンバランスの変化に対応するためには、自律神経が働いています。
月経周期は女性ホルモン以外にもさまざまなホルモンで調整されていますが、ホルモンバランスの変化に、気圧の変化や寒暖差、湿度などの変化が加わることで、自律神経の働きが過剰になってしまうのです。
また、更年期の女性も、女性ホルモンが急激に低下してホルモンバランスが乱れやすくなっているため、気象病が起こりやすくなります。
さらに、その人の気質も気象病との関係があると考えられています。神経質な人や、精神的ストレスを受けやすい人、ストレスがかかると身体に湿疹などの変化が現れる人も気象病になりやすいと言えます。
梅雨時期の体調不良の症状とは?
梅雨のように長い期間天気が崩れると、気象病としてさまざまな症状が起こります。
一口に頭痛と言っても、こめかみがズキズキと痛くなる、キューッと締め付けられているような痛みなど感じ方には個人差があります。
その他に、天気が引き起こす体調不良は以下です。
□ めまい
□ 耳鳴り
□ 気管支喘息
□ 神経痛
□ 古傷の痛み
□ 気分のおちこみ
など
このような症状がいくつか当てはまる方は、医療機関で診察を受けることをおすすめします(上記はあくまでもチェックリストであり、診断を確定するものではありません)。
梅雨時期の頭痛をやわらげる対処法
梅雨時期の頭痛をやわらげるには、十分な睡眠をとる、ぬるめの湯船につかる、ストレッチをする、ストレス解消することなどを心がけてみましょう。
十分な睡眠は、自律神経を整えるために欠かせません。梅雨時期は気圧の変化や湿度から寝苦しく感じたり、なかなか寝付けなかったりすることもあります。そのためには、ぬるめの湯船につかり体を温めるのもおすすめです。湯船につかりリラックスしたり、就寝前にストレッチしたりすると、入眠しやすくなります。
またストレスを溜めないことも大切です。
ストレスは自律神経の働きにも大きく関わるため、体を動かしたり趣味の時間を設けたり、してストレスを溜め込まないように工夫してみましょう。
日常生活でできる頭痛の予防方法
雨の日に起こるなんとなくだるい、頭痛、めまいなどの症状は普段からの生活を見直すことでも予防や対処ができます。梅雨時期や秋にかけては雨や台風の機会も多くなるため、今日から予防を始めましょう。
自律神経のバランスを整える
気象病は自律神経の乱れが大きな原因です。自律神経のバランスを整えるには、生活リズムを整えましょう。決まった時間に十分な睡眠を取る、適度な運動、朝食をきちんと摂ることを意識することが大切です。
また朝起きて明るい陽射しを浴びることも体内リズムを整えて、夜に入眠しやすくします。寝る前のスマホは交感神経を刺激するため控えましょう。
耳周辺・肩・首の血流を良くする
頭部や肩・首の筋肉が緊張して日常的に凝っていると、血流が悪くなります。耳周辺の血流が悪くなると、内耳のリンパ液も滞ってめまいや頭痛を引き起こします。
そのため、日ごろからマッサージをして凝りをほぐすことが大切です。マッサージグッズを使って気になる箇所をほぐしたり、ヨガやストレッチなど行ったりすることも効果が期待できます。
また適度な運動は、全身の血流を良くします。特定の部位なら筋トレ、全身の運動ならウォーキングや水泳がおすすめです。無理のない範囲で取り入れてみましょう。
梅雨時期の頭痛などの症状が長く続いたらまずは専門医に相談を
梅雨時期になると起こる頭痛などの症状は、気象病かもしれません。気象病は自律神経の乱れが原因となり、頭痛のほかにだるさやめまいなどの症状が起こることもあります。
まずは、生活リズムを整えてストレスを溜め込まない生活を心がけましょう。
その上で、症状が長引く場合は、医療機関の受診を。専門医に相談し、詳しい検査を受けることが大切です。
大清水クリニックでは、患者様の症状を和らげ、快適な毎日をお過ごしいただけるよう診療に努力いたします。
また大清水クリニックでは、子供の頭痛はもちろんのこと、めまい・しびれに悩む女性に寄り添った治療もご提案しています。
つらい頭痛・めまい・しびれ等にお困りの方は名古屋市緑区の大清水クリニックへお気軽にご相談ください。